シマエナガとは?
シマエナガは、日本の北海道に生息するエナガの亜種で、「雪の妖精」とも呼ばれる小鳥です。
体長は約14cmほどですが、そのうち尾が半分以上を占め、丸くてふわふわした白い顔が特徴的です。
冬になると真っ白な雪景色と溶け込むような姿を見せ、その可愛らしさから近年は写真やグッズで大人気となっています。
雑食性で、小さな昆虫やクモ、木の実などを食べ、群れで生活する習性があります。
この記事には広告(アフィリエイトリンク)が含まれています。
(楽天市場の商品リンク)シマエナガの基本情報
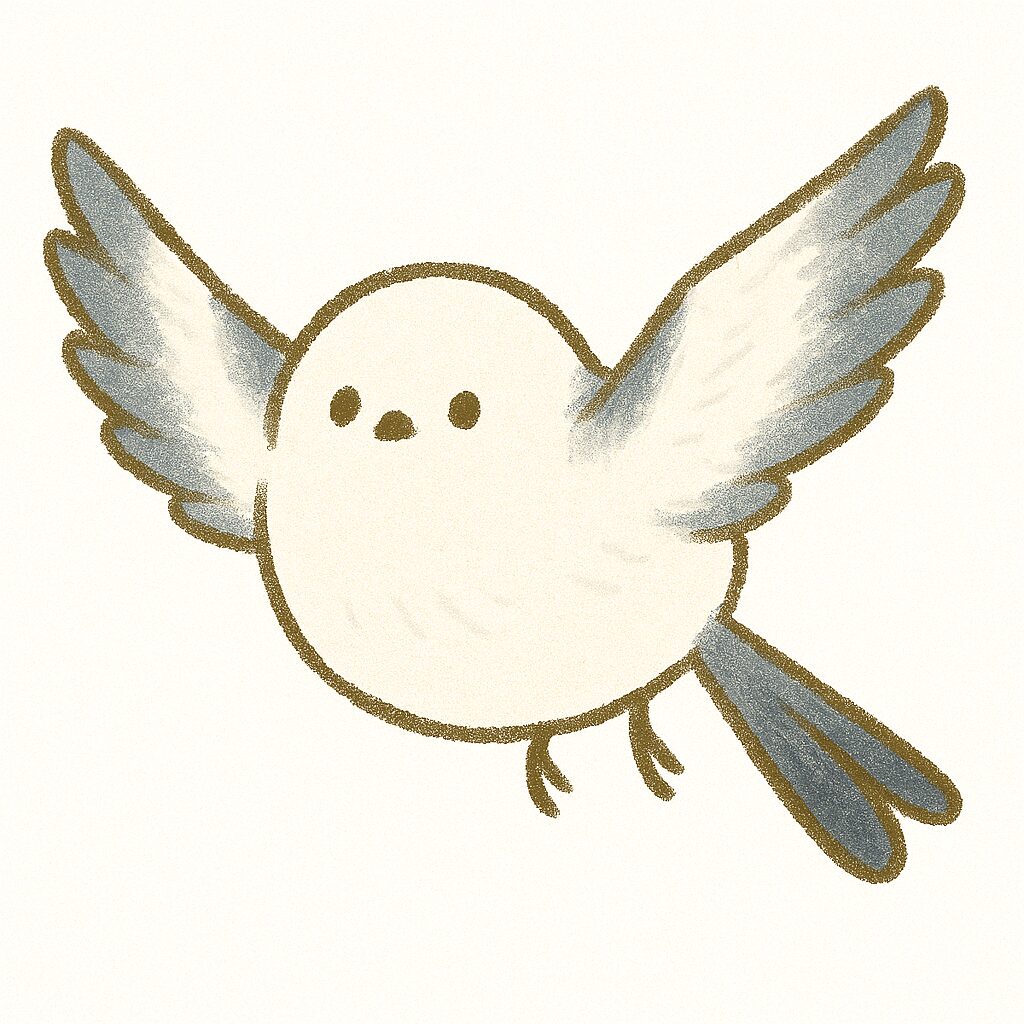
- 分類: スズメ目 エナガ科
- 分布: 日本(北海道のみに分布)
- 体長: 約13〜15cm(うち尾は7〜9cm程度)
- 体重: 約7〜9g
- 特徴: 真ん丸い白い顔と小さな黒い目、「雪の妖精」と呼ばれる愛らしい姿
- 食性: 昆虫、クモ、木の実などを食べる雑食性
- 寿命: 野生下で約2〜3年(長く生きる個体は5年程度とされる)
シマエナガの進化

シマエナガは、エナガ科に属する鳥で、エナガの亜種とされています。
もともとエナガはユーラシア大陸全域に広く分布しており、日本では本州以南にエナガ(基亜種)、北海道にシマエナガが分布しています。氷期と間氷期の気候変動の中で、北海道の個体群が孤立して適応進化し、顔全体が白いという特徴的な外見を持つようになったと考えられています。
この「顔が真っ白」という特徴は、寒冷な雪景色の中での保護色として役立った可能性が指摘されています。
シマエナガの生態

シマエナガは、主に北海道の森や林に生息し、冬になると数羽から十数羽の群れを作って移動します。
体は小さいですが活発で、枝から枝へと飛び回りながら昆虫やクモを捕食し、秋から冬には木の実や種子も食べます。
巣作りの際はコケや羽毛を集めて丸い巣を作り、外敵から身を守る工夫が見られます。
また寒さに強く、雪が積もる季節でも活発に活動できる適応力を持っています。
さらに詳しく知りたい方は、Wikipediaのエナガも参考になります。
シマエナガの豆知識

冬に丸くなる理由
シマエナガは冬になると体をふくらませ、まんまるの姿になります。これは寒さをしのぐために羽毛の間に空気をため、断熱効果を高めているからです。
群れで行動する習性
繁殖期以外は10〜20羽ほどの群れで行動し、互いに鳴き声を出し合いながら移動します。小さな体でも群れで動くことで、天敵から身を守る効果があります。
巣作りの工夫
シマエナガは苔やクモの糸を利用して巣を作ります。クモの糸は伸縮性があるため、雛が成長しても巣が壊れにくい仕組みになっています。
本州のエナガとの違い
本州のエナガは目の周りに黒い線が入っていますが、シマエナガにはそれがなく、顔全体が真っ白です。この違いから「雪の妖精」と呼ばれ、特に写真愛好家に人気です。
シマエナガに会える可能性のある場所
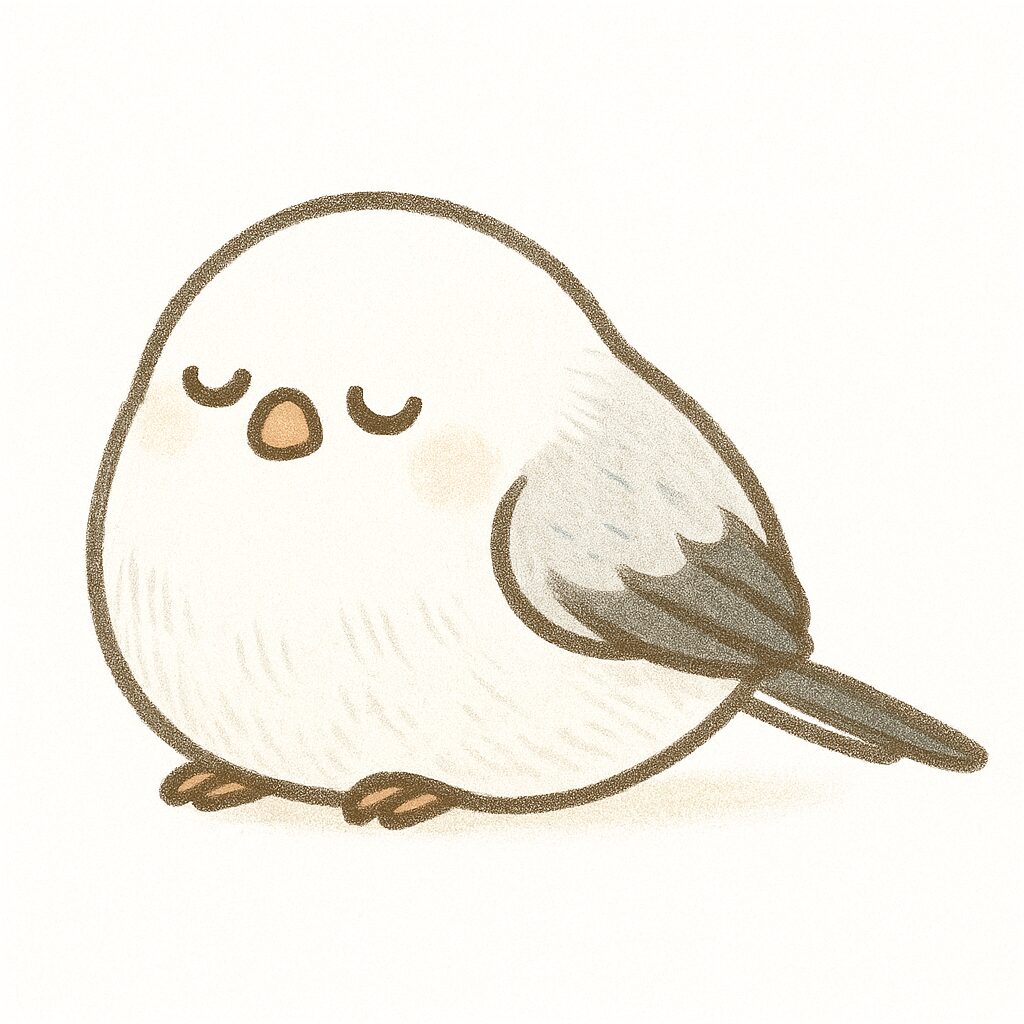
① 旭山記念公園(札幌市)
札幌郊外にある高台の公園で、森林と開放空間が混在しており、シマエナガの目撃率が高い場所とされています。 公園内には「森の家」という施設があり、野鳥情報が発信されることも。
② 円山公園(札幌市)
都市部近くの自然豊かな公園。冬季にはシマエナガが街中へ下りてきて目撃されることがあります。
③ 国営滝野すずらん丘陵公園(札幌市)
広大な森林エリアと温帯林を含む国営公園。冬季は「滝野スノーワールド」としても開放され、シマエナガ観察スポットとして紹介されることがあります。
④ 青葉公園(千歳市)
千歳川沿いにある公園。樹木が多く自然度が高いため、シマエナガの目撃例が比較的多いスポットとされています。
⑤ ウトナイ湖・周辺エリア(苫小牧市)
ウトナイ湖周辺自然保護区や観察散策路でシマエナガを探すことができる可能性があります。湖畔の森や湿地の周辺が観察ポイント。
⑥ 知床・釧路・春採公園(東北海道エリア)
知床国立公園、春採公園(釧路市)など、原生林や湿地が残る地域でもシマエナガの生息が報告されています。自然度の高い場所で、冬期〜通年で観察される可能性あり。
シマエナガの関連グッズ
シマエナガのグッズはこちら(楽天市場の商品リンク)
本記事のリンクから購入されると、当サイトに報酬が発生する場合があります。
シマエナガの画像
シマエナガのリアル写真








シマエナガのイラスト
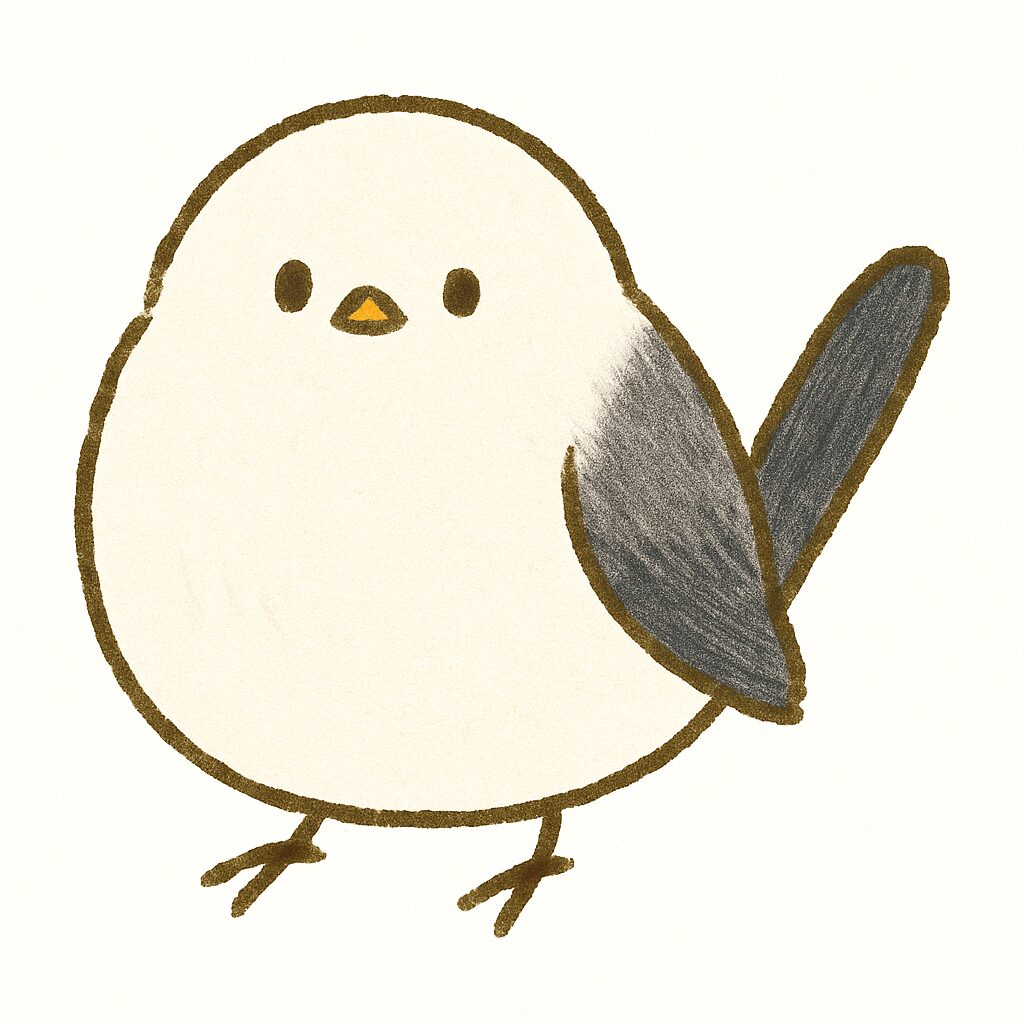
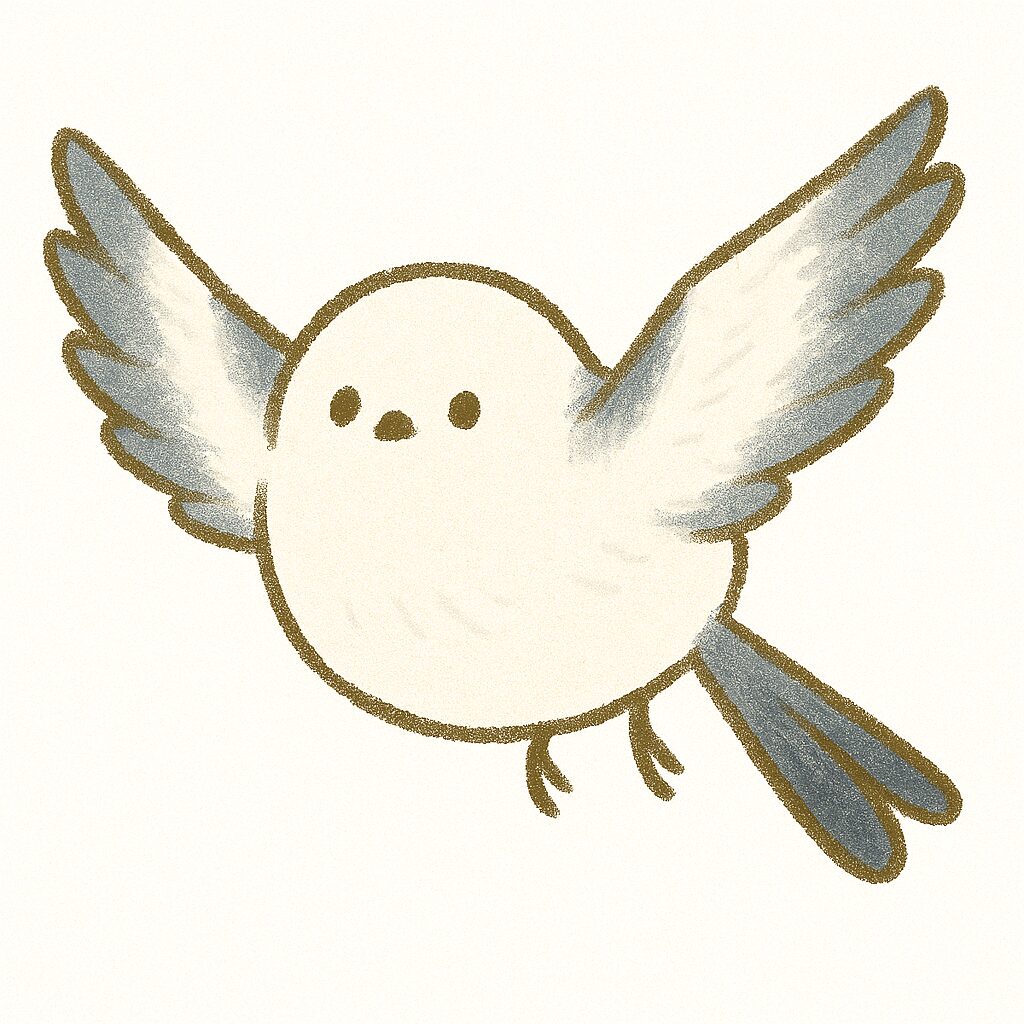



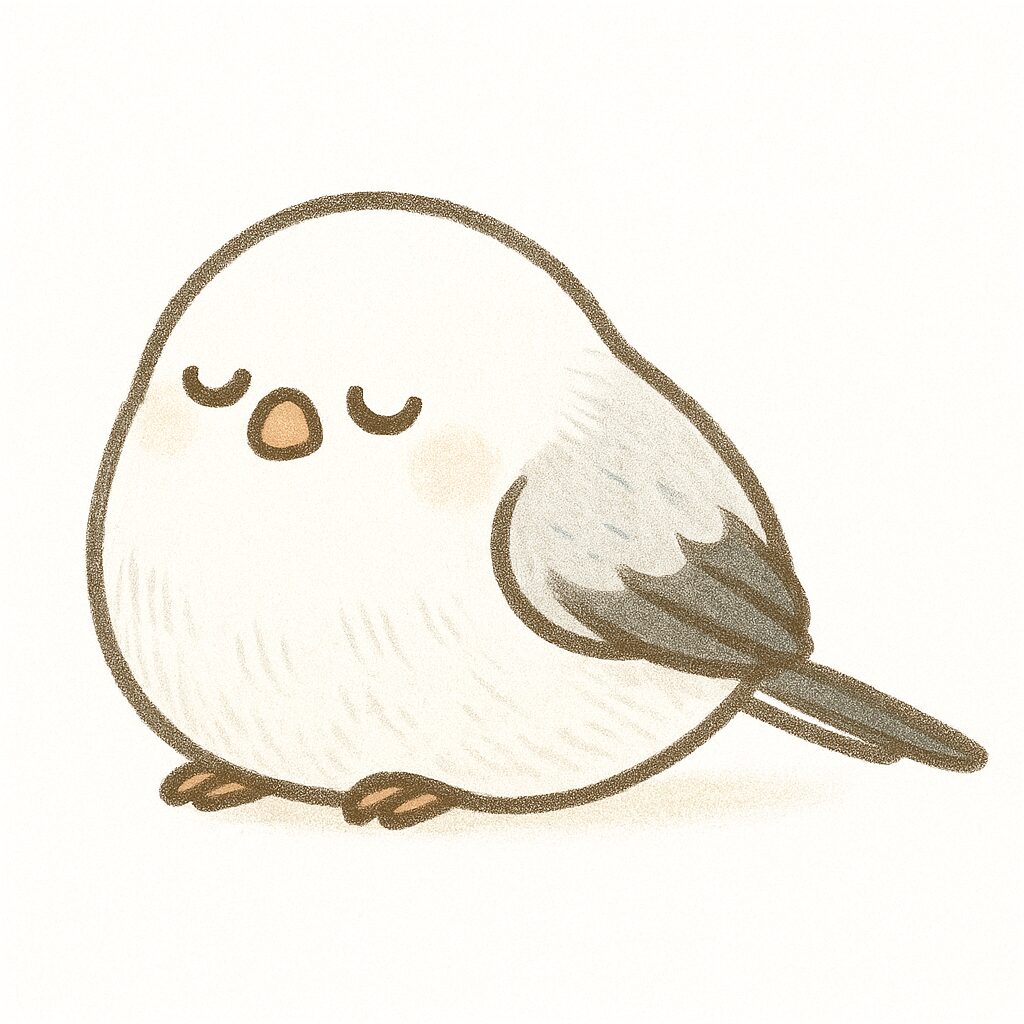
※このサイト上の画像はAI生成によるものです。利用規約をご確認ください。








コメント